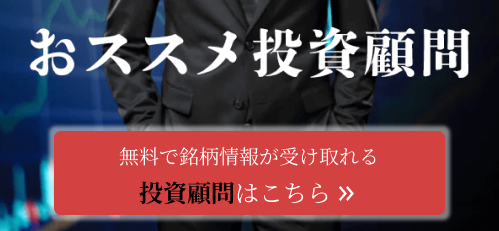こんにちは、億トレサラリーマンです。
2月13日、ホンダと日産が進めていた経営統合に向けた協議を打ち切ると報じられました。
自動車業界がEV(電気自動車)シフトや自動運転技術の進化といった大きな変革期を迎える中、日本を代表する2社の統合は業界再編の象徴となる可能性がありました。しかし、結果として両社は統合を断念し、それぞれ独自の道を歩むことになりました。
そもそも、ホンダと日産はなぜ統合を模索したのでしょうか。その背景には、急速に進むEV・ソフトウェア開発競争や、トヨタ・海外メーカーとの激しい競争がありました。特に、スケールメリットを生かしたコスト削減や技術開発の加速は、統合によって得られる大きなメリットと考えられていました。しかし、交渉が進むにつれ、企業文化の違いや戦略の不一致が浮き彫りになり、最終的には決裂に至ったとされています。
この経営統合に向けた協議の決裂はホンダ・日産にどのような影響を及ぼすのでしょうか。
この記事では、統合交渉の背景や決裂の理由やホンダや日産は今後どうなっていくのかについてお話ししていきます。
ホンダと日産、経営統合交渉が決裂ーー何が起こった?
ホンダと日産は13日、それぞれの取締役会で、昨年12月に締結した基本合意書を撤回し、経営統合に向けた協議を終了することを決定しました。協議を打ち切る理由について、両社は「迅速な意思決定や経営施策の実行を優先するため、統合を見送るのが適切だと判断した」と説明しています。
当初、両社は持ち株会社を設立し、その傘下に入る形での経営統合を目指していました。しかし、ホンダはその後、経営の主導権を強化するため、日産の株式を100%取得して完全子会社化する案を提案。さらに、この案を受け入れなければ協議の継続は困難だとの立場を示しました。これに強く反発した日産は、経営統合の協議を終了する意向をホンダに伝えていました。
一方で、両社は昨年8月から進めてきたソフトウェアの研究開発やEV(電気自動車)分野での協業については、今後も連携を継続するとしています。
今回の経営統合の協議は、EVやソフトウェアの開発力強化、コスト削減を狙いとしていましたが、打ち切りにより両社は戦略の見直しを迫られることになります。特に、業績が低迷する日産にとっては経営再建が急務となり、収益性改善に向けた具体策の実行が重要な課題となります。
統合の背景:なぜホンダと日産は交渉を進めたのか?
そもそも、日本を代表する自動車メーカーの2社はなぜ経営統合に向けて交渉を進めたのでしょうか。その背景には、両社ともに抱いていた自動車産業の将来における強い危機感がありました。
現在、自動車メーカーの競争の軸になっているのは、エンジンや走行性といったハード面から、EV(電気自動車)などの脱炭素に向けた「電動化」や、自動運転などの「知能化」へと移りつつあると言われています。実際に、2024年の世界の自動車販売台数を見てみると以下のような状況になっています。
2024年自動車販売台数ランキング
| 順位 | 自動車メーカー | 販売台数(万台) |
|---|---|---|
| 1 | トヨタグループ|日本 | 1082 |
| 2 | フォルクスワーゲングループ|ドイツ | 902 |
| 3 | ヒョンデグループ|韓国 | 723 |
| 4 | ステランティス|フランス | 543 |
| 5 | GM|アメリカ | 517 |
| 6 | BYD|中国 | 427 |
| 7 | フォード|アメリカ | 395 |
| 8 | ホンダ|日本 | 380 |
| 9 | 日産自動車|日本 | 334 |
| 10 | スズキ|日本 | 324 |
2024年自EV販売台数ランキング
| 順位 | 自動車メーカー | 販売台数(万台) |
|---|---|---|
| 1 | テスラ|アメリカ | 172 |
| 2 | BYD|中国 | 168 |
| 3 | 吉利自動車グループ|中国 | 81 |
| 4 | GM|アメリカ | 77 |
| 5 | VWグループ|ドイツ | 71 |
| 6 | ヒョンデグループ|韓国 | 38 |
| 7 | BMWグループ|ドイツ | 37 |
| 8 | 広州自動車グループ|中国 | 36 |
| 9 | 長安自動車グループ|中国 | 30 |
| 10 | ステランティス|フランス | 24 |
| 20 | トヨタグループ|日本 | 13 |
| 21 | 日産自動車|日本 | 12 |
| 26 | ホンダ|日本 | 5 |
ご覧の通り、自動車販売台数だけでみると日本メーカーは世界的に見てかなりのシェアを占めていますが、ことEV販売台数を見てみるとアメリカや中国のメーカーが大きく先行していることが分かります。EVやプラグインハイブリッド車に強みを持つ中国のBYDは40%も販売台数を伸ばし、ホンダや日産自動車を抜き販売台数世界6位のメーカーまで躍進しています。アメリカや中国の振興メーカーは着々と力を付け、日本メーカーとの差はどんどん広がっていると言えるでしょう。EV販売は一時期の勢いほどはないとはいえ、脱炭素時代に備えるのであれば開発をしないというわけにはいきません。
日産:最終赤字800億円”業績立て直し”が課題
日産自動車は13日、今年度の決算見通しを修正し、これまで未定としていた最終損益が800億円の赤字となる見込みだと発表しました。販売の不振が続いているアメリカ市場でのテコ入れのための費用や、大幅な人員削減にかかる費用を損失として計上したうえでの見通しのようです。売上高に関しても、これまでの見通しより2000億円少ない12兆5000億円、営業利益は300億円少ない1200億円を見込んでいます。
日産自動車の業績立て直しには大規模な構造改革とあわせて商品力の強化が大きな課題となっています。
ホンダ:競争を勝ち抜くための”規模の拡大”が課題
今年度グループ全体の最終利益9500億円を見込むなど、業績自体は堅調なホンダも決して安泰ということではありません。
バイク事業は高い利益水準を出しているが、自動車事業の収益性の改善はテコ入れが不可欠。さらに、テスラやBVDなどの振興メーカーが台頭するなかで、世界のライバル企業との競争を勝ち抜くためには、先進技術の開発にかかる膨大な費用の分担や効率化が必須であり、それには企業としての規模の拡大が必要と考えられています。
両メーカーそれぞれが強い危機感を抱えるなか、規模の拡大を通じて、EVやソフトウェアの開発の強化、協業によるコストの削減などを進める狙いで経営統合の協議が進められてきたという形となりました。
交渉決裂の理由は?主要な対立点を解説

経営統合の協議に関する報道が出た際、日産の株価は上昇した一方、ホンダの株価は大きく落ち込みました。投資家心理としては、業績不振の日産との統合ということになればホンダの経営の足枷になるという受け止められ方をしてもおかしくはありません。しかし、ホンダは統合に向けた本気度を示すべく、最大1兆1000億円の自社株買いを発表。これにより、既存株主への配慮を示すとともに、株価の下落を食い止める狙いもあったと見られます。こうした動きは、ホンダが経営統合を単なる日産の救済という観点ではなく、将来的な成長戦略の一環として本気で推し進めようとしていたことを物語っています。
当初、両社は持ち株会社を設立し、その傘下に両社を置く形での経営統合を目指していました。この方法であれば、両社の独立性を一定程度維持しながらも、資源の共有やコスト削減などの相乗効果を期待できる形となります。しかし、協議が進む中で、ホンダ側には日産の経営姿勢に対する不満が募っていきました。
「日産の経営立て直し計画が踏み込みが甘い」
「意思決定がことごとく遅い」
「経営陣は会社や社員のことを考えていないのではないか」
「統合協議にあまり時間をかけていられない」
といった点が問題視されました。ホンダとしては、競争が激化する自動車業界において、素早く意思決定を行い、新しい技術開発や事業戦略を進めることが不可欠だと考えていたため、日産の慎重すぎる対応に苛立ちを募らせていたのです。こうした状況を受け、ホンダは統合の枠組みを変更し、日産を完全子会社化するという案を提案しました。ホンダが日産の経営を直接掌握することで、意思決定のスピードを上げ、事業の方向性をより明確に打ち出すことを狙ったものです。しかし、この提案に対し、日産側は強く反発しました。
これを受けて日産側は、
「完全子会社化したら日産の精神は守られるのか」
「日産が持つポテンシャルを引き出せるのか」
特に、日産は過去に経営危機を乗り越え、独自の技術開発力やブランド価値を築いてきた歴史があります。そのため、ホンダの傘下に入ることは、自社のアイデンティティを損なう可能性があると懸念したのです。結果的に、日産はホンダの提案を拒否し、経営統合協議の打ち切りを申し出ました。
この交渉決裂を受けて、「日産はプライドを捨てられないままでいいのか?」という声も多く上がっています。一方で、ホンダの焦りすぎた対応にも疑問を投げかける意見があります。どちらの主張もそれなりに理があるものの、長い歴史を持つ二つの企業が一つになることの難しさが、今回の交渉過程を通じて改めて浮き彫りになったと言えるでしょう。
経営統合は実現しなかったものの、両社は今後もソフトウェア開発やEV分野での協業を継続するとしています。しかし、業績回復が急務の日産にとっては、自社単独での再建がより厳しい道のりとなるのは間違いありません。今後、どのような戦略を打ち出すのかが注目されます。
業界への影響:ホンダと日産はそれぞれ今後の戦略は?

経営統合に向けた交渉の決裂から、それぞれ強い危機感を持ったホンダと日産は今後どのような課題があり、どのような戦略をとっていくことが必要でしょうか。
ホンダの今後の課題と戦略
経営統合の協議が打ち切られたことで、ホンダは今後の成長戦略を見直さざるを得ない状況に直面しています。
現在、ホンダの業績は比較的堅調に推移しているものの、自動車事業の収益性向上は長年の課題とされてきました。特に、グローバル市場における電動化の波が加速する中で、ホンダはEV(電気自動車)やプラグインハイブリッド車(PHEV)の競争力強化が急務となっています。例えば、中国市場ではEVの需要が急速に拡大しているものの、ホンダは地元の新興メーカーや欧米メーカーとの競争に苦戦し、販売不振が続いています。世界最大の自動車市場である中国でのシェア低下は、ホンダにとって大きな課題であり、今後の戦略転換が求められる状況です。
こうした背景から、ホンダはEVやソフトウェア技術の競争力を高める手段として、規模の拡大を狙い日産との経営統合を模索しました。日産との統合によって、技術開発のリソースを共有し、コスト削減や新技術の迅速な市場投入を目指していたのです。しかし、協議が決裂した今、ホンダは新たな提携戦略を模索する必要があります。
その中で注目されるのが、ホンダがEVや燃料電池システムの開発で提携しているアメリカのゼネラルモーターズ(GM)との関係です。ホンダとGMは、次世代EVプラットフォームの共同開発を進めており、これまでに複数の電動車両の共同開発計画を発表しています。しかし、GM自身も提携戦略を多角化しており、2024年9月には韓国のヒョンデ(現代)自動車と新車の開発・生産からサプライチェーンまでを含む包括的な業務協力に向けた覚書を締結しました。これは、GMがホンダ以外のパートナーとの連携を強化し、より広範な提携関係を築こうとしていることを示しています。
自動車業界では、競争力を維持するために提携が不可欠となっており、すでに多くの大手メーカーがグローバルな協力体制を構築しています。例えば、トヨタはスバルやマツダと協力しながらEV技術を開発しており、フォルクスワーゲン(VW)もフォードと提携しEVと自動運転技術の開発を進めています。こうした状況の中で、新たな提携相手を見つけることは容易ではなく、ホンダにとっても選択肢が限られているという指摘があります。
ホンダが今後どのような戦略をとるのかは、業界内外から大きな注目を集めています。日産との統合という道が閉ざされた今、単独でのEV事業強化を進めるのか、それとも新たな提携先を模索するのか。今後のホンダの動向が、自動車業界の競争構図にも大きな影響を与えることになりそうです。
日産の今後の課題と戦略
業績の悪化が続く日産にとって、経営の立て直しは待ったなしの課題です。特に、グローバル市場における販売不振や、過剰な生産能力の問題を抱える中で、コスト構造の抜本的な見直しが急務となっています。今後、日産が生き残るためには、生産体制の適正化や固定費の削減を着実に進め、収益性を回復できるかどうかが問われることになります。
まず注目されるのは、2024年11月に公表した大規模なリストラ計画の実行です。この計画では、世界全体の生産能力を20%削減し、それに伴い約9000人の人員削減を行うことが発表されました。この削減策をどこまでスムーズに実行できるかが、短期的な業績改善のカギを握ります。特に、日本国内や欧米市場では、生産拠点の整理や統廃合が避けられない状況となっており、現地の雇用やサプライチェーンへの影響も懸念されています。こうした課題をクリアしながら、日産が経営のスリム化を実現し、財務基盤を強化できるかが重要なポイントとなります。
さらに、単にコストを削減するだけではなく、将来の成長に向けた投資戦略も求められています。EV(電気自動車)市場が急速に拡大する中、日産は競争力を維持するための新たな技術開発や生産体制の強化を進めなければなりません。しかし、経営統合の協議が決裂したことで、単独での生き残り戦略を再構築する必要に迫られています。そのため、今後は新たな提携先の検討を含めた経営戦略の見直しが不可欠となるでしょう。
こうした状況の中、日産の経営に対して新たな動きも見られています。台湾の大手電子機器メーカー「ホンハイ精密工業(Foxconn)」が、日産の経営への参画を水面下で検討していたことが明らかになりました。ホンハイは近年、自動車分野への進出を積極的に進めており、EVの生産やバッテリー技術の開発に注力しています。経営統合が見送られたことで、ホンハイが日産の株式取得に動くのではないかという見方も広がっています。
これに関連して、ホンハイ精密工業の劉揚偉(リュウ・ヤンウェイ)会長は12日、日産の筆頭株主であるフランスのルノーと協議したことを明らかにしました。さらに、その際に日産の株式取得についても話し合われたものの、単なる買収ではなく協力関係の構築が目的であるとの考えを示しました。ホンハイとしては、日産と提携することでEV生産の拡大を目指し、将来的にはより深い協力関係を築く可能性もあると考えられています。
このような動きを受けて、日産の長年の提携相手であり、多くの株式を保有するフランスのルノーの対応も今後の焦点となりそうです。ルノーは日産とのアライアンスを維持しつつ、すでにEV技術開発において独自の戦略を進めています。そのため、ルノーが日産の経営戦略にどのように関与するのか、またホンハイとの協力関係をどこまで受け入れるのかが、今後の日産の経営方針に大きな影響を与えることになるでしょう。
協議再開は?ホンダと日産の経営統合は完全に打ち切られた?
2月19日、ホンダは日産自動車の内田誠社長が退任すれば経営統合の交渉を再開する意向であると英フィナンシャル・タイムズが報じました。
日産自動車は内田社長の退任時期についての非公式な協議を開始したとのことです。
両社の経営統合の協議がスムーズに進むことがあれば、世界を代表する両社がひとつとなって自動車業界にも色々な影響が出てくることが予想されます。個人的には、日本のメーカーが世界のライバル達との競争を勝ち抜いていくことが理想的だと思っているので、両社納得のいく形で経営統合が為され、さらに競争力を付けて戦って欲しいですね。
「億トレサラリーマンのここではかけない特別銘柄をLINEで配信しています。宜しかったらLINE登録お願いします。」

億トレサラリーマンの「無料銘柄でも高いパフォーマンス!期待のテーマ株を多数配信する」注目するべき投資顧問一覧はコチラ↓
株情報サイト&メルマガ情報
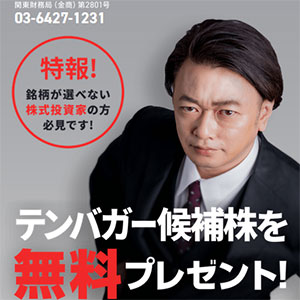
橋本罫線考案者の故・橋本明男さんの意思を引き継ぐ稲垣社長や、グローバルな見地からコラムを執筆する王さんなどバラエティに富んだサイト。無料登録で「テンバガー候補銘柄」などプレゼント中。

高山緑星こと前池英樹さんが社長を務めるサイト。「2036年までの未来予測」を完了しているとしており、本当に株価の動きを読むのが上手い人と感じています。無料銘柄でも大きく勝てる可能性あり。
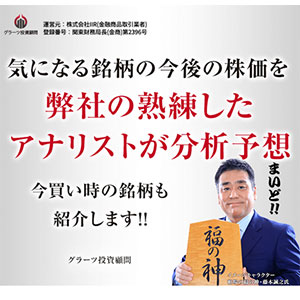
グラーツ投資顧問は、相場の福の神 藤本さんのコラムやカブ知恵代表取締役の藤井英敏さんのコラム「投資の方程式」などを無料掲載しているサイト。アドレス登録で「大本命3銘柄」を無料提供。